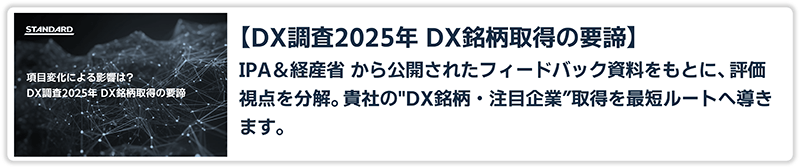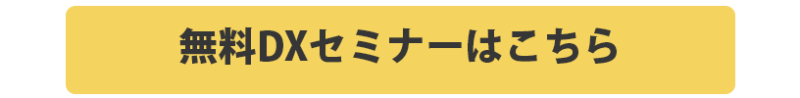DX推進は何から始めればいい?よくある失敗例と押さえるべきポイント
この記事の目次
DXの推進部署を立ち上げたものの、「何から手をつければいいのかわからない」というのはよく聞かれる悩みです。実際にDXで成果をあげている日本企業はごくわずかだという話を耳にして、今後に不安を感じている担当者の方も少なくないでしょう。
DXの成功確率は、その推進方法によって大きく左右されます。そこで、本記事ではDXへの取り組みが失敗する理由と、成功に向けて押さえるべきポイントについてご説明します。また、DXの実現を目指す多くの企業で共通の課題となっている人材育成についても触れるので、参考にしてください。
DX推進によくある失敗の理由
DXは、顧客にとって価値の高い商品やサービスを提供できる組織・文化を、継続的に創り続けていく取り組みです。具体的な施策は企業ごとに異なりますが、デジタル技術とデータを活用する点など、共通する部分もあります。まずは、DXの推進がうまくいかない理由として、よくある例を紹介します。
DX推進のプライオリティが低い
DX以前から、現場はそれぞれの仕事を抱えています。急に「DXをやるぞ」と言われても、優先的に取り組めるだけの人的・時間的な余裕があるとは限りません。担当者がDXの必要性を熱心に説明したところで、関係部署からの理解や協力を得られないこともあるでしょう。
このような「温度差」は、DXのプライオリティが部署によって異なるために生じています。そのまま放置すれば、DXに関する活動は事実上の停止状態に追い込まれるかもしれません。しかし、その間にも市場ではデジタル化が進み、ビジネス環境は刻々と変化していきます。DXを実現できないままでいると、既存市場の中でさえ取り残されるリスクがあることを理解すべきでしょう。
DX推進をIT部門任せにしている
DXは組織全体におよぶ変革であり、全社一丸となって取り組むべき活動です。ところが、現実としてはDXをIT部門任せにしてしまう企業が少なくありません。もちろん、社内システムの刷新をともなうものであることから、DXにはIT部門の協力が欠かせません。しかし、IT部門の一存で新システムを構築しても、事業部門の要求を満たすことは難しいでしょう。
たとえDXの分野で実績のある外部ベンダーの協力を得たとしても、この状況は変わりません。外部ベンダーがIT部門としか話をできないようでは、改善が必要なビジネスプロセスや解決すべきビジネス課題もわからないためです。結果として、「ただシステムが新しくなっただけ」でDXが終わってしまうことも考えられます。
DXに対する理解にバラツキがある
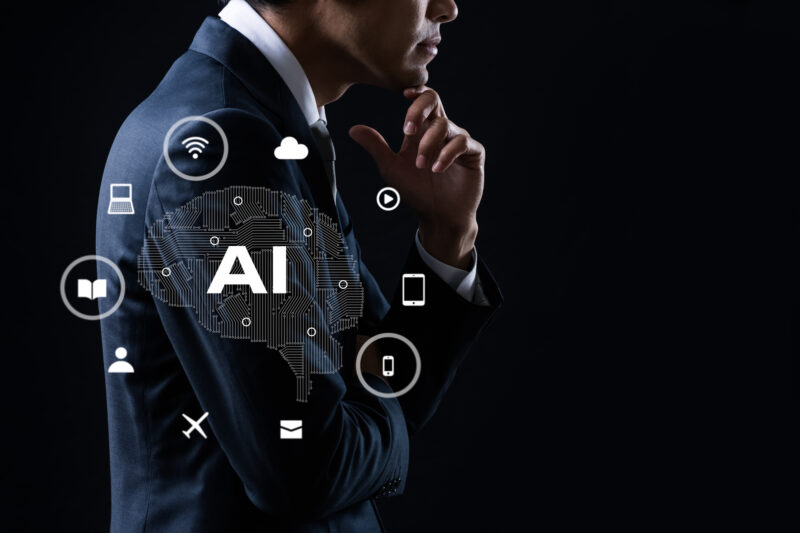
実りのあるDXのためには、DXで何を目指し、何を解決するのかといった話し合いが必要です。しかし、関係者間でDXそのものの理解にバラツキがある状況では、議論を有意義に進めることは難しいでしょう。
例えば、AIなどのデジタル技術に関して知識が不足しているために、具体的なアイデアが出てこないかもしれません。あるいは、最新の技術を用いたところで、そのアイデアの実現性の検証が十分に行えないケースも考えられます。
これは、DXに関する基礎的な知識を共通のものとしない限り、質の高いアイデアは生まれないことを意味しています。もし、アイデアの質が不十分なままで実行に踏み切ったとしたら、何が起こるか想像してみましょう。いつまでも成果を出せない活動にコストを投入し続けることを考えれば、そのリスクの大きさがわかるでしょう。
デジタル技術を使うことが目的化している
DXは、解決すべき課題があってこそ取り組む価値があるものです。「トレンドだから」や「他社に遅れをとりたくないから」といった理由だけではじめるものではありません。「AIを使って何かしたい」のような、明確なビジョンをともなわない動機もDXがうまくいかない要因です。デジタル技術の活用が目的化してしまう状況は、よくある失敗のパターンだと認識すべきでしょう。
企業によっては、「老朽化したシステムを刷新したい」という課題を抱えていることもあるでしょう。しかし、これはDXとともに解決すべき課題であって、DXそのものではありません。システムの刷新が自己目的化すると、新システムがその後のDXを阻害する要因となり、「再レガシー化」に陥るリスクがあります。また、本来であれば長期的に取り組むべきはずのDXが、一過性のブームで終わってしまうことも考えられます。
アイデアの投資対効果が検証されていない
業務改善の成否を投資対効果で判定するのは、企業にとってごく自然なことです。DXについても、思ったほどの効果が得られなければ「失敗」とみなされるでしょう。
このような事態は、DXを実行に移す前に、必要な投資と期待される効果について十分に検証しなかった場合に起こります。例えば、他社の成功事例を聞きつけ、「ぜひ自社でも同じことを」と深く考えずに手をつけてしまったケースです。DXの実現に求められる施策は企業ごとに異なるため、他社の真似をしただけでは十分な効果は期待できません。
とはいえ、失敗を恐れるあまり何もできないというのも問題です。成果が保証できないために実行に移す決断をせず、有望なアイデアから目を背けてしまうことも考えられます。満足のいく成果を得るためには、行動を通して失敗に学び、小さな軌道修正を繰り返しながら進んでいく姿勢も必要です。
DXを推進できる人材が確保できていない
DXの実現には、DXに適した人材が必要です。今後の基盤となるシステムの要件を明確化したり、その構築を進めたりするには、DXとデジタル技術の知識・スキルが求められます。しかし、そのような人材は不足しているのが現状です。
人材確保をあきらめて、DXに関するすべてを外部ベンダーに委ねるという選択もあるでしょう。ただし、その場合は外部ベンダーにとって都合のよい提案を鵜呑みにしてしまうリスクを避けられません。外部ベンダーが既存のビジネスプロセスや現場の業務フローを十分に理解しないままシステムを構築すると、最悪の場合、「コストをかけたのに誰も使ってくれない」ということもあり得ます。また、自社内にノウハウが蓄積されず、システムの内製化も進まないという状況に陥りかねません。
関連記事:【DX失敗事例から学ぶ】DX推進に立ちはだかる3つの課題と成功要因
経済産業省の「DX推進ガイドライン」と「DX推進指標」

経済産業省は、日本企業がDXを実現するための課題と対応策について検討し、その結果を「DXレポート」(『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』)として取りまとめました。また、これを基に「DX推進ガイドライン」と「DX推進指標」を策定しています。
これらは、DX推進において日本国内の企業が直面する共通の課題を解決するための手掛かりとして活用できるものです。ここでは、「DX推進ガイドライン」と「DX推進指標」の概要について紹介します。
DX推進ガイドライン
「DX推進ガイドライン(デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン)」は、「DXレポート」における提言を基に経済産業省が策定したガイドラインです。
本ガイドラインは、「(1)DX推進のための経営のあり方、仕組み」と「(2)DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」の2部構成になっています。それぞれの中では、DXを実現していくうえでのアプローチや必要なアクションについて言及されています。よくある失敗ケースについても併記されているので、DX推進の担当者はいちどは目を通しておくとよいでしょう。
ガイドラインを活用すれば、DXの実現やそのためのシステム構築で押さえるべきポイントがわかります。また、DXの取り組み状況を株主などが把握する目的にも利用可能です。
なお、DX推進ガイドラインは2022年9月に「デジタルガバナンス・コード2.0」に統合されています。詳細については、以下の記事で解説していますので併せて参考にしてください。
関連記事:DX推進ガイドラインとデジタルガバナンス・コードの要点を解説!
DX推進指標
「DX推進指標」は、「DXレポート」と「DX推進ガイドライン」の内容を踏まえ経済産業省が策定した指標です。
本指標は、「DX推進ガイドライン」の構成に対応する「DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標」と「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標」の2部構成になっています。それぞれの中では、DX推進の成熟度を6段階で評価する定性指標と、取り組み状況を数値化して把握するための定量指標が示されています。
これらの指標は、各企業がDX推進の状況を自己診断するためのものです。自社の課題を認識し、関係者間で共有して具体的なアクションにつなげるための気付きを得るツールとして活用できます。必要な項目について継続的に評価や測定を行えば、DXプロジェクトの進捗状況の把握やDX施策の効果測定などにも活用できるでしょう。
DX推進で押さえるべきポイント

「DX推進ガイドライン」や「DX推進指標」には、日本企業がDXを推し進めていくために役立つヒントが体系的に網羅されています。しかし、DX推進の初期段階では、どの部分に重点を置いたらよいのかわかりにくいかもしれません。そこで、ここからはDXに取り組みはじめて間もない企業が押さえておくとよいポイントについて紹介します。
DXのビジョンを共有する
企業がDXで成果をあげるには、経営層がDXという変革に「本気」であるという姿勢を示すことが重要です。ビジネスのあり方から人事の仕組みや働き方、企業の文化・風土まで含めたドラスティックな変化を推し進める際に、経営層によるコミットメントがあれば力強い後押しになります。
そのためには、将来のビジョンを明確化し、組織全体で共有する必要があります。デジタル技術により価値のある商品・サービスを生み出していく創造性や、市場の変化に対応しながら企業としての競争力を維持していく柔軟性などを、ビジョンや経営戦略としてまとめるとよいでしょう。
DXへの協力体制を整える
全社一丸となってDXを推進するためには、組織内で相互に協力できる体制づくりが不可欠です。部門の垣根を超えたコミュニケーションを意識すれば、DXが部門内部の局所最適に陥るような事態も防ぎやすくなります。具体的な取り組みとしては、経営層と事業部門、IT部門など、互いに協力すべき各部門の人員から構成された「DX推進部署」を設立する方法などが考えられます。
当初は少人数のタスクフォースから、DX推進活動をスタートさせたいケースもあるでしょう。その場合でも、各部門から十分な支援を得られるように配慮すれば、企業の文化や風土としての定着を目指して全社的な取り組みに育てていくことができます。
DXの知識レベルを揃える
DXを力強く推進できるかどうかは、DXそのものの知識レベルにも左右されます。組織内の知識レベルを底上げし、全社共通の下地としましょう。これにより、DXは新たな「リテラシー」になります。デジタル技術を用いて何ができて、何ができないのかを各自が理解すれば、議論と検証を通して斬新で実現性の高いアイデアが生まれる可能性も高まります。
このとき、DXの起点となるのは「ヒト」だということを念頭におくべきでしょう。DXとはデジタル技術の導入を指すものではなく、デジタル技術を手段として用いながら組織を変化させていく活動です。全社的な取り組みとしてDXを継続していくためにも、DXのリテラシー化により各自の知識レベルを一定水準以上に揃えることが大切です。
関連記事:DXリテラシーとは? | 誰に必要なのか、何を学ぶことなのか?徹底解説!
DXで解決したい課題を明確にする

DXでは、企業の経営戦略やビジョンに基づいて、解決すべき課題を明確化することが重要です。その根底には、市場の変化に適応しながら顧客への提供価値を高め、企業としての競争力を維持し続けるというテーマが存在します。この点を意識していれば、デジタル技術の導入ばかりが目的化するような事態に陥ることはないでしょう。
DXの課題が明確になっていれば、それにともなうシステムの刷新もうまくいく可能性が高くなります。DXの基盤として有用なシステムには、「いつでも柔軟に改修できる構造にしたい」という要件が必要になるためです。これにより、システムの刷新が一過性のもので終わることがなくなるとともに、再レガシー化も防げます。
質の高いDXのアイデアを抽出する
DXの課題は経営戦略やビジョンに基づくべきだといっても、すべてがトップダウンで決まるとは限りません。社内にあるさまざまな課題と、それらを解決するためのアイデアを現場から抽出することも大切です。良質なアイデアであれば、コストばかりにとらわれることなく実行に移す決断も可能でしょう。アイデアの質を確保するには、ある程度の量も必要になります。
アイデアの量と質をどちらも確保するためのポイントは、DXのリテラシー化を前提とすることです。DXの知識レベルが底上げされれば、AIをはじめとする最新のデジタル技術からさまざまな着想を得られるようになります。その中から、現実的で投資対効果の高いアイデアもみつかるかもしれません。
DXの人材を社内で育成する
DXを推進していくには、社内での推進方法に関する基本的な知識のほか、AIやデータ活用といった実践的なスキルも必要です。これらの知識・スキルを備えた人材の確保は、多くの企業が抱える課題となっています。
DXの初期段階では、社外の人材に頼らざるを得ないこともあるでしょう。しかし、その場合でも、自ら人材を育てていく姿勢が大切です。自社内で対応できる範囲を広げていけば、DXに関するノウハウも蓄積されていきます。システムの内製化を進めながら、最終的には自社の人材だけでDXを継続できるように人材育成に取り組むとよいでしょう。
関連記事:DX人材に必要なスキルと社内育成の重要性について徹底解説!
DX推進に必要な人材を社内で育成するには

DXのための人材育成では、まず組織的なリテラシーの獲得により知識レベルの底上げを行うことが大切です。そのうえで、DXの推進役となる人材に専門的なスキルの習得を促していきます。
ただし、DXにおいては新たに身につけるべきスキルが従来の業務の延長線上にあるとは限りません。業務内容の変化や、まったく新しい業務にも対応できるスキルを身につけてもらう必要があるのです。そのためには、「リスキリング」が多くの企業にとって重要な施策になるでしょう。
効果的なリスキリングのためには、求める人材像を明確にして育成に取り組む必要があります。その際の指針として活用できるのが、経済産業省とIPAが策定した「デジタルスキル標準(DSS)」です。
経済産業省とIPAが策定した「デジタルスキル標準」とは
「デジタルスキル標準(DSS)」とは、DXにどのような人材が必要となるかを汎用的な表現で定義したものです。DXの実現を目指すあらゆる企業が、自社の方向性などに合わせて具体化することで人材育成に活用できます。
デジタルスキル標準は、以下の2つの指針から構成されています。
– 「DXリテラシー標準(DSS-L)」:2022年3月に公表
– 「DX推進スキル標準(DSS-P)」:2022年12月に公表
ここでは、これらの概要について簡単に説明していきます。より詳しい内容を知りたい方は、以下の記事も併せて参考にしてください。
関連記事:経産省の「デジタルスキル標準」が示すDX人材育成の2つの指針とは
DXの基礎的な知識とスキルを示す「DXリテラシー標準(DSS-L)」
「DXリテラシー標準(DSS-L)」は、DXに参画するあらゆる人材(経営層も含む)が、DXに必須のリテラシーを身につけるための指針となるものです。
DXリテラシー標準は、以下の4つの大項目で構成されています。
– マインド・スタンス
– Why(DXの背景)
– What(DXで活用されるデータ・技術)
– How(データ・技術の利活用)
いずれもDXに当事者意識をもち、主体的に行動するために学習すべき項目です。
また、急速に発展しつつある「生成AI」についても触れられているので、一度は目を通しておくとよいでしょう。生成AIは企業におけるDXの進展と競争力の向上に大きく貢献する可能性のある技術ですが、効果的に活用するには、データとの向き合い方やモラル・リスクへの認識を新たにする必要があります。
なお、各項目の詳細については、以下の記事でも解説していますので併せて参考にしてください。
関連記事:「DXリテラシー標準(DSS-L)」が示す企業変革のための行動と学習の指針とは
DX推進に求められる役割とスキルを示す「DX推進スキル標準(DSS-P)」
「DX推進スキル標準(DSS-P)」は、DXを推進する人材を以下の5つに大別して定義したものです。
– ビジネスアーキテクト
– デザイナー
– データサイエンティスト
– ソフトウェアエンジニア
– サイバーセキュリティ
それぞれが果たすべき役割と、求められるスキルが整理されています。
「DXリテラシー標準(DSS-L)」がすべてのビジネスパーソンを対象としているのに対し、「DX推進スキル標準(DSS-P)」は、DX推進で中心的な役割を果たす人材を対象としています。つまり、DXにはここで挙げた5種類の人材が必要だということです。社内のすべての人材を5種類に分類するという意図ではありません。
DXの推進には、これらの人材が専門的なスキルを習得し互いに助け合いながら、周囲の人材をも巻き込んで取り組みを牽引していくことが大切なのです。
なお、各人材の詳細については、以下の記事でも解説していますので併せて参考にしてください。
関連記事:「DX推進スキル標準(DSS-P)」が定めたDX人材に求められる役割とは
デジタルスキル標準を人材育成に取り入れるポイント

あらかじめ分類・整理されたDXのスキルを自社にあてはめて考えることができれば、本当に必要な人材像を明確にしたうえで、最適な人材育成を進められます。デジタルスキル標準を、DXの実現に向けた人材育成に取り入れるメリットは大きいといえるでしょう。
そのためには、リテラシー教育がDX推進の下地になるのだという点を忘れないことが最初のポイントです。そのうえで、DX推進を担う5種類の人材のスキルマップを定義し、育成カリキュラムを作成していきましょう。
また、スキルの習熟度をどのように把握していくかを考えることも重要なポイントです。育成状況にあわせて個別にスキルアップを促すためには、人材ごとの成長の度合いを継続的に追跡・可視化できる仕組みが求められます。
デジタルスキル標準を活用してDXにおける人材育成の課題を克服
企業がDXを実現できるかどうかは、その推進方法によって大きく変わってきます。ありがちな失敗を避けながら、ポイントを押さえて成功確率を高めましょう。なかでも人材育成とDXに関する知識レベルの底上げは、DXで成果を出したい企業にとって共通の課題です。
それらの課題を解決するためにはデジタルスキル標準を活用しながら取り組むのが効果的です。とはいえ、汎用的な形で定義された知識やスキルを、自社にあてはめて具体化していくのは簡単ではないと感じる方も少なくないでしょう。
そこで、自社に必要な人材育成をデジタルスキル標準に準拠させる方法について解説するホワイトペーパーをご用意しました。以下のボタンから無料でダウンロードできますので、DX人材の育成計画策定にぜひお役立てください。