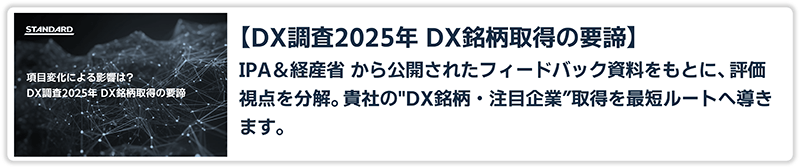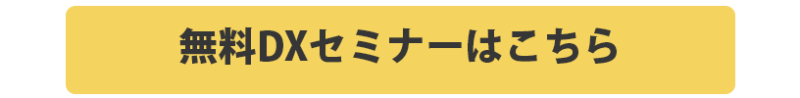DX推進するならまず目指すべきDX認定とは?メリットや申請手順を解説
この記事の目次
DXに取り組んでいる企業のなかには「DX認定」の取得を目指している企業も多いのではないでしょうか。DX認定を取得すると、経済産業省からDXへの取り組みを認めてもらえ、それによって社会的な評価や企業価値の向上につながったり、「DX投資促進税制」の優遇措置を受けることができたりとメリットも多くあります。
この記事では、DX認定制度の内容やDX認定を取得することのメリット、取得のための申請手順、デジタルスキル標準などを詳しく解説していきます。DX認定について知りたい方や取得を目指している経営者の方はぜひ参考にしてみてください。
DX認定制度とは

まずはDX認定制度について、どのような制度なのかやその制度の背景を解説していきます。
経済産業省のDX推進事業者に対する認定制度
DX認定制度とは、経済産業省がDX推進の準備が整っている事業者を認定する制度です。認定の審査をするのは、経済産業省所管の独立行政法人のIPA(情報処理推進機構)となっています。DX認定のレベル感としては、ビジョンの策定や戦略、体制の整備ができていて準備が整っている「DX-Ready」の状態です。
与信管理ASPクラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社(以下、リスモン)が行った「第1回『DX認定企業』分析」(※)では、2022年6月時点のDX認定事業者415社の状況がまとめられています。
そのレポートのなかで、まず415社しかDX認定を受けていないということは、日本の法人企業数は500万社といわれているなかで日本企業全体のわずか0.0008%しか認定を取得していないことになると指摘されています。取得している事業者は、意欲的にDXに取り組む希少な企業といえるでしょう。
またレポート内でのDX認定事業者の一覧の分析では、上場企業や売上高・資本金規模の大きい企業が名を連ねています。さらに、リスモンが提供する信用格付けであるRM格を見ると高格付(A~C格)企業が全体の8割超を占めていて、信用力という基準においても、評価の高い企業がDX認定を取得していることがわかります。
(※)出典:リスクモンスター株式会社| 調査結果発表:第1回「DX認定企業」分析(リスモン調べ)
デジタルガバナンス・コード2.0とは
デジタガバナンス・コード2.0とは、DX推進において経営者が実践するべきことがらをまとめたものです。DX認定の審査を行うIPAの定義では、「企業のDXに関する自主的取組を促すため、デジタル技術による社会変革を踏まえた経営ビジョンの策定・公表といった経営者に求められる対応をまとめたもの」(※)となっています。また、DX認定制度の申請にあたって記入する各項目は、デジタルガバナンス・コ ード2.0の項目と対応しています。
DX認定制度の背景
2019年に「DX推進指標」が策定されましたが、IPAによる「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート」では大部分の日本企業がDXに未着手か、着手していても成熟度がかなり低い状態で、DXにうまく取り組めていないという状況が見えてきました。
そこで日本全体でもっとDX推進がなされるようにと、DX認定制度が生まれました。企業にはDX認定制度の取得を目標にしてもらうことで、DX推進の準備ができているレベルがどのような状態かを把握してもらい、まずはそのレベルに達せるように目指してもらうことが可能となります。それによってDX推進を徐々に日本企業全体に浸透させるのが狙いです。
DX認定を取得する3つのメリット

DX認定制度の取得は企業にとってもメリットがあります。ここでは以下の3つのメリットについて紹介します。
DX 投資促進税制が活用できる
DX認定を取得することでDX投資促進税制の優遇措置を受けることができます。優遇措置では、DXを推進するにあたってこの税制措置の対象となるものの費用に関しては、税額控除や特別償却を受けることが可能です。デジタル技術や設備の導入にかかる費用の負担が減るのはメリットといえます。
DX 投資促進税制とは
DX投資促進税制とは、企業がDXに取り組む際に必要となるデジタル技術や設備の導入といった投資費用を負担する優遇措置のことです。
税制措置の対象となるのは、ソフトウェアやそれと連携して使用する器具や備品、または繰延資産などで、原則3%の税額控除または特別償却30%の措置を受けることが可能となります。DX投資促進税制が適用されるのは2023年3月31日までです。期限が迫っているので早めにDX認定の取得を目指すと良いでしょう。
DX投資促進税制についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
プライム上場企業の場合「DX銘柄」の選定条件が満たせる
「DX銘柄」とは、DXを推進するための仕組みを社内に構築し、デジタル活用の実績がある企業で、なおかつ東京証券取引所に上場しているプライム上場企業のなかから業種区分ごとに選定されて紹介するものです。
このDX銘柄に選ばれるには、DX認定の取得が条件の一つとなっています。DX銘柄に選ばれることで、投資家や社会から高い評価を得られるというメリットがあります。
DX銘柄についてさらに詳しく知りたい方は、こちらも記事もぜひ読んでみてください。
国がランキングするDX銘柄や成功企業の事例を知り、自社の参考にしよう
ロゴマークを利用できDX推進をアピールできる
DX認定を取得すると、DX認定ロゴマークを使う権利が得られます。ロゴマークを自社のパンフレットや名刺などに載せることで、DXに積極的に取り組んでいる企業として認識され、企業価値やブランドイメージの向上につながります。
DX認定を取得するための詳細

ここからは、DX認定制度を利用できる対象や取得までの期間、申請手順を詳しく解説していきます。
DX認定制度の対象
DX認定制度の対象は全ての事業者で、公益法人なども含めた法人と個人事業者が対象です。申請にあたっては、他にも要件があるため詳細は「申請要項(申請のガイダンス)」を確認してください。
申請からDX認定取得までの期間
申請は1年を通していつでも可能です。申請から認定取得までの期間は通常約60営業日となっています。
ただし土日祝日は含めないため、実カレンダー上の日数では約3ヵ月かかることになります。さらに、多くの審査が集中した場合や、審査の締め日の兼ね合いでさらに時間がかかる場合もあるため、申請から認定取得までは4ヵ月以上は見ておくと安心です。
DX認定取得の申請手順
以下、申請手順の概要を説明していきます。
- 「申請のガイダンス」の確認
- 必要提出書類のダウンロードと準備
- Web申請システムで申請及び、必要書類の提出
①「申請のガイダンス」の確認
まずDX認定制度の申請にあたっては、各種必要となる準備や手順などがまとめられた「申請要項(申請のガイダンス)」をしっかりと確認する必要があります。
ただし、申請要項(申請のガイダンス)は、改訂される可能性があるため、DX認定制度において審査をしているIPAのWebサイトも合わせて確認しましょう。
②必要提出書類のダウンロードと準備
新規で認定取得をする場合は、以下の書類をダウンロードする必要があります。ダウンロードは、IPAのWebサイトから可能です。新規の認定申請も更新の申請も費用は全て無料となっています。
添付資料が必要な場合もあります。詳しい内容の記載方法や事前準備については「申請要項(申請のガイダンス)」を確認して、書類の準備をしましょう。
◎新規申請書類
- DX認定制度 認定申請書
- DX認定制度 申請チェックシート
③Web申請システムで申請及び、必要書類の提出
書類が準備できたら、Web申請システム「DX推進ポータル」から申請をして、必要書類の提出をします。この申請システムの利用には、gBizID(ジー・ビズ・アイディー)の取得が必要です。「申請要項(申請のガイダンス)」で詳細なやり方を確認できます。
認定取得後の更新対応
DX認定の取得後は、DX推進ポータルのWebサイトの「認定事業者一覧」に掲載されます。この認定は有効期間が2年間です。
認定の更新をする場合は、認定後2年を経過する日の60日前までに更新の申請をします。更新に必要な書類は、IPAのWebサイトからダウンロードが可能です。
申請の手順はこれまでに説明してきた手順とほとんど同じですが、「申請要項(申請のガイダンス)」で詳しく書いてあるため、申請前は確認をしましょう。
DX認定に向けた社内環境構築の例
DX認定に向けて社内環境を構築してきた福島コンピューターシステム株式会社様の例を紹介します。
福島コンピューターシステム株式会社様は、福島県郡山市に本社を置く、独立系のシステムインテグレーター(SIer)として、「業務系」「制御系」「組込系」の3分野のシステム開発を行い、多くの企業に最適なシステムを提供しています。
DXへの取り組みは、自社でこれまで扱っていなかったマルチクラウドへの対応やアジャイルでの開発といった要望を顧客から受けたことがきっかけです。新しいデジタル技術にも対応できるようにと、従来の開発方法や企業の姿勢を変えようと考え、DXに取り組み始めました。
DXの推進にあたっては、まずはDX推進チームを結成。さらにSTANDARDのDXリテラシー講座を社内全員で受講し、DXに対する知識や認識を社内で共通化させてスムーズにDX推進を進めていくための土台を固めていきました。
それによってデジタル技術などの活用の仕方を理解するとともに、DXを通して何を実現したいのかというDXの本質への理解も深め、「顧客の課題解決や成長促進に寄与する提案ができるようになる」という目標を掲げて、従業員が一丸となってDXに取り組んでいます。このようにしてDXを推進するための社内環境を構築し、現在はDX認定の取得を目指しています。
「導入事例」からは、STANDARDの「DXリテラシー講座」を実際に導入されDXを進めている他の企業の方の声も読むことができるので、ぜひ参考にしてみてください。
「デジタルスキル標準」を活用した人材育成

DXを推進するにあたって自社の人材育成をしていくのに役立つ「デジタルスキル標準」があります。ここでは、デジタルスキル標準とは何かを詳しく説明し、これを活用した人材育成の方法について解説します。
デジタルスキル標準(DSS)とは
「デジタルスキル標準(DSS)」は、DXを実現するためにどのような人材を育成すべきかを示した指針です。
DX推進をしている企業は増えてきていますが、まだまだ遅れをとっている企業は少なくありません。DXの実現のためには、経営者も従業員もDXについて理解して、自分事として全社一丸となって取り組むことが大切です。そのためには、一人一人の従業員にDXに関するリテラシーを身につけさせ、デジタル技術やデータの活用など専門性を持った人材を確保・育成することが必要となります。
そこで役に立つのが、デジタルスキル標準(DSS)です。自社のDXを進めるにあたって、どのような人材を育成すべきかを考える参考となるからです。
デジタルスキル標準(DSS)は、DXリテラシー標準(DSS-L)とDX推進スキル標準(DSS-P)の2種類で構成されています。以下でそれぞれどのようなものなのか詳しく解説します。
DXリテラシー標準(DSS-L)
「DXリテラシー標準(DSS-L)」とは、全てのビジネスパーソンに向けたもので、DXに関する基礎的な知識やスキル・マインドを身につけるための指針です。項目としては、DXの背景や、DXを推進するためのデータやデジタル技術、それらの活用方法、DXのマインドスタンスについて、それぞれの学習すべき内容が示されています。
企業はDXリテラシー標準を活用して従業員を教育することで、DXリテラシーを身につけ させることができます。すると、自社のDXの取り組みも加速することができます。まだDXに本格的に取り組んでいない企業・組織、ビジネスパーソンは、将来的なDXの取り組みに備えてリテラシーを身につけておくことが大切です。
5-1-2. DX推進スキル標準(DSS-P)
「DX推進スキル標準(DEE-P)」とは、DXを推進するための専門性を持った人材を育成・採用するための指針です。
日本企業がDXを推進する人材を十分に確保できていない背景として、自社に必要な人材を把握しづらいという課題があると考えられています。DX推進スキル標準では、企業のDXの推進において必要な人材のうち、主な人材を以下の5つの「人材類型」に区分して定義し、さらに、各類型のロールやスキルも示しています。
DX推進スキル標準を参考にすることで、自社のDXではどのような専門的な人材、スキルが足りていないのかを把握しやすくなります。これによって適切な人材育成の方向性を知り、従業員の教育を進めることが可能です。
- ビジネスアーキテクト
DXの取り組みにおいて目的設定から導入、導入後の効果検証までを一気通貫して推進する人材。
- デザイナー
製品・サービスの方針や開発のプロセスを策定し、それらに沿った製品・サービスのありかたのデザインを担う人材。
- データサイエンティスト
データを収集・解析する仕組みの設計・実装・運用を担う人材。
- ソフトウェアエンジニアリング
デジタル技術を活用した製品・サービスを提供するためのシステムやソフトウェアの設計・実装・運用を担う人材。
- サイバーセキュリティ
デジタル環境におけるサイバーセキュリティリスクの影響を抑制する対策を担う人材。
デジタルスキル標準の活用方法
デジタルスキル標準をどのように活用することで、自社の人材育成に役立てることができるのでしょうか。ここでは、活用方法を解説します。
自社に必要なスキルを考える
まずは、自社ではDXをどのように進めていくのか、具体的な目標や取り組み内容を明らかにしておくことが大切です。その上で、DX推進スキル標準を活用して、自社のDX推進に必要なスキルを特定しましょう。
DX推進スキル標準では、5つの人材類型ごとに求められる知識・スキル・マインドが定義されているので、自社のDX推進戦略と照らし合わせながら、各人材類型ごとにどのようなスキルを育成していく必要があるのかを検討します。
このとき、自社の現状を把握することも重要です。現状の自社のスキルを把握することで、育成すべきスキルの優先順位を決めることができるからです。
現状を把握するためには、従業員一人一人が持つスキルを、客観的に可視化すると良いでしょう。従業員のスキルの全体像を把握するのに、スキルの名称やレベル、関連性などを記載したスキルマップを作成すると自社の保有するスキルの全体像を把握しやすくなります。
DX人材育成の教育を行う
DX人材育成の教育を行う際には、eラーニング、OJT、外部研修などさまざまな教育方法を組み合わせるのが有効です。学習者のニーズや状況に合わせて、効果的な学習環境を提供することができるからです。以下は教育方法の例を紹介します。
- eラーニング
eラーニングとは、インターネットやパソコンを使って学習を行うことです。eラーニングは、時間や場所を問わず学習を進めることができるため、忙しいビジネスパーソンにもおすすめです。
- OJT
OJTとは、OJTとは、On-the-Job Trainingの略で、実務を通して学習を行うことです。OJTは、実践的なスキルを身につけることができるというメリットがあります。
- 外部研修
外部研修とは、外部の研修会社が提供する研修を受講することです。外部研修は、専門的な知識やスキルを短期間で身につけることができるというメリットがあります。
実務での実践する
教育を行ったら、実務での実践機会を提供することも大切です。実践機会を提供することで、従業員は習得した知識・スキルを実際に活用することができ、その成果を客観的に評価してもらうことで、学んだことを実践で活用する力が養われ、さらに学習意欲も高めることができるからです。
具体的な実践機会としては、例えば社内プロジェクトや社外コンテストなどに参加してもらったり、社内業務の改善提案をしてもらうなどがあるでしょう。具体的な実践機会を提供して、従業員が自社のニーズや課題を見つけ、それに対してデジタル技術やデータを活用して解決のための実行ができるようになることが重要です。
まずはDX人材育成に取り組むのがおすすめ

これまでにDX認定の内容や、メリット、取得のための申請の方法を解説してきました。福島コンピューターシステム株式会社様の事例でもわかるように、まずはDXに対する知識や認識を経営陣、従業員ともに共通化させ、DX推進の社内環境の構築をすることでスムーズにDXを進めることができます。DX認定取得を目指すなら、まずはDXリテラシーを身につけさせる社内の人材育成が重要です。
弊社では、デジタルスキル標準(DSS)に準拠して、DX人材育成をどうやって進めれば良いのかを解説したお役立ち資料をご用意しております。デジタルスキル標準を具体的にどう自社で活用すればいいのかわからない、活用方法を知りたいという方は、下記より本サービスの資料をダウンロード頂けますので、ぜひご活用ください。