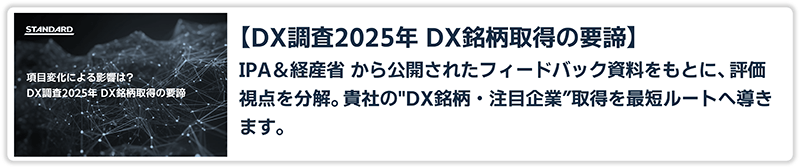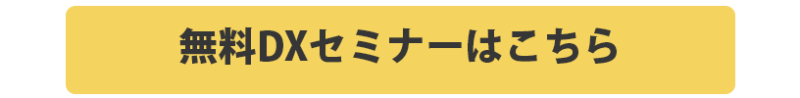DX推進におけるリスキリングの重要性と推進手順
この記事の目次
DX推進において「リスキリング」を耳にする担当者も多いのではないでしょうか。今回の記事では、DX推進におけるリスキリングの重要性と推進メリット、先進事例から見えてきたリスキリングの本質、リスキリングの際に活用できる補助金やデジタルスキル標準などについて詳しく解説していきます。
リスキリングの目的と重要性

まずは、リスキリングとはどのような施策で、なぜ企業にとって重要なのかについて以下の観点から整理して説明します。
- リスキリングとは誰が何を学ぶためのものか
- リスキリングはDX推進の原動力となる重要な取り組み
リスキリングとは誰が何を学ぶためのものか
「リスキリング」という用語の意味については、2021年2月に経済産業省により開催された「デジタル時代の人材政策に関する検討会」のなかで議論された、次の定義が有名です。
「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」
DXを推進する企業においては、「今後予想される業務内容の変化に備え、従業員にスキルを獲得してもらうこと」がリスキリングなのだといえます。つまりリスキリングは、DXの担当者のみが対応すればよいという話ではなく、社内の誰もが対象となる可能性があるものです。まずはこのことを頭に入れておきましょう。
リスキリングはDX推進の原動力となる重要な取り組み
リスキリングとは「新しくスキルを獲得すること」を意味しており、よくDX推進の文脈で用いられる用語です。DXの取り組みでは、企業の価値創出に向けて、自社バリューチェーンの様々なプロセスに変化/変革を迫ります。その際に、まずは価値創出に向けた土台作りを行っていきますが、各プロセスにおけるアナログな業務がデジタルへと置き換わる必要があります。なぜなら、企業の価値創出には、全社的な情報共有・データ連携が必要不可欠だからです。「リアルタイムに様々な部門・部署から情報が引き出せ、集めた情報を即座に欲しいアウトプットとして可視化できる」といった体制を構築することが求められます。
また、アナログ業務をデジタルへと置き換える際に、WEBサービスやITツールを活用することはもはや必須となっており、「誰がデジタル化への移行作業を行うか」ではなく「全員がデジタルに強くなる」ことが求められている現状があります。つまり、DX推進において、バリューチェーンの各プロセスに最適な人材(IT人材/DX人材)を確保・配置するのは時間とコストがかかり過ぎるため、現在の人材リソースで対応することが求められているのです。
そうしたDX推進の実態を鑑みると、「DXの内製化」や「既存の人材リソースのリスキリング」などのDX戦略は、企業の実態に即した推進方法となります。リスキリングは、企業の人的資源をアップグレードする役割を担い、困難ともいえるDXの大目標を達成するための力強い原動力となるでしょう。
リスキリングと似た人材育成の用語

人材育成に関しては、リスキリングとは異なるものの混同されがちな用語もあります。リスキリングに取り組む際には、こうした違いについて理解しておくと役立つ場面もあるでしょう。ここでは、以下について説明していきます。
- アップスキリングとの違い
- リカレント教育との違い
アップスキリングとの違い
リスキリングと似た用語に「アップスキリング」があります。アップスキリングとは、「今やっている仕事・職種の延長線上で、上位の業務に就くこと」を意味します。つまり、昇進や昇格、それに伴うスキル習得がアップスキリングとして解釈されます。
一方のリスキリングは、企業の各バリューチェーンにおいて、それぞれの人材が新たに習得するスキルを指します。リスキリングの特徴は、例えばアナログな業務からデジタルの業務へと転換するために、エンジニアリングスキルやAI実装スキルなどを習得することにあるため、既存業務の延長線上のスキル習得ではない性質を持っています。
DXとは本来、企業の価値創出に向けて、バリューチェーンの全体的な変革をも視野に入れた取り組みとして推進されます。したがって、企業のDXの捉え方、あるいは推進ステップの違いで、アップスキリング/リスキリングが当てはまります。
リカレント教育との違い
リカレント教育は「社会人の学び直し」を意味しており、学校教育から離れた社会人が再び大学などの教育機関で学び直す行為を指しています。リカレント教育の目的は、「それぞれの人が必要なタイミングで再び学校教育を受けることにより、仕事やプライベートの充実度を高めていこう」というものです。職場におけるアップスキリングの要素もありますが、どちらかといえば、より良い人生を送るための「QOL向上」や「ウェルビーイング」の文脈で用いられる用語です。仕事や職場への影響を考えて実施する学び直しであればアップスキリングの要素を含み、より良い人生を送るための学び直しであれば生涯学習の要素を含むと考えれば良いでしょう。
対するリスキリングは、主にビジネスの場(DXの文脈)で用いられる用語です。現職の延長線上のスキル習得(アップスキリング)ではなく、DXによるバリューチェーンの変革も視野に入れたスキル習得になります。
DX推進企業にリスキリングが注目される理由

リスキリングと似た用語の違いを確認した後は、なぜDX推進でリスキリングが注目されるのかを見ていきましょう。理由としては、主に以下の4つが挙げられます。
- 先端技術を活用した競争力強化が求められる為
- DX人材の確保が難しい為
- 採用コストの削減
- 業務効率化・生産性向上
それぞれの理由について解説していきます。
先端技術を活用した競争力強化が求められる為
DXでは企業の価値創出において、各バリューチェーンの変革が求められ、しばしばアナログ業務からデジタル業務への転換が必要になります。その際、AI・RPAを搭載したITツールを活用したり、専門的な技術実装によって稼働するロボティクスを配置したりと、これまで経験したことのないスキル習得・業務遂行に追われます。
近年、様々な業界で、先端技術を活用したビジネスモデルを展開する新規参入企業が増え、既存の商習慣を変革する「デジタルディスラプション(デジタルによる破壊)」が起こっています。そのような事態に対応するために、企業はDX戦略の中で「先端技術を活用した価値創出」を推進の軸に据えることが多くなっており、DX推進の取り組みで先端技術を活用することはもはや必須といえます。先端技術を導入するにあたり、企業は先端技術を使いこなし、管理する人材を必要としますが、その際に取り組むべきなのがリスキリングなのです。
DX人材の確保が難しい為
DX推進は経営戦略のトレンドとして各企業に認識されているため、DX推進を力強く牽引するDX人材は引く手あまたの状況です。そのような転職市場の中、DX人材の確保を自社の採用戦略に据えることはあまり現実的でないため、「既存の社員のスキルアップを図り、変化するバリューチェーンにどうにか対応していこう」という動きが出てきます。こうした葛藤の中で取り組まれるのがリスキリングであり、たとえ最適な人材を確保できたとしても、自社の変化に対応するための継続的な学びは求められるため、DXを推進する企業にとって、リスキリングは避けられない課題といえるでしょう。
採用コストの削減
DX人材の確保が難しいこともあり、DX人材の転職市場における価値は日々上昇しています。そこで企業は、専門スキルを持った人材を確保するために多額の採用コストを投じるのではなく、既存の社員をリスキリングする形で、新たな変化に対応していく必要があります。全社的なリスキリング計画をたてれば、全社員のスキルアップデート後の体制構築を検討でき、採用コストも削減できます。
業務効率化・生産性向上
DX推進でぶつかる壁の1つに「既存社員への説明・コミットメント」があります。現場社員にとって、経営層からDX推進の十分な説明と手引きがない場合、DX推進へのコミットメントは低くなります。特に推進初期は、既存業務を遂行しながら新しい業務を覚える必要があり、現場社員への負担が増加します。そのような環境の中でも現場社員の高いコミットメントを得るために、リスキリングによる業務効率化・生産性向上が必要になるのです。リスキリングによって得た新たな知識は、新たな業務に適応するためのスキルだけでなく、既存業務を効率的に進めるためのヒントも与えてくれます。現場社員の中で小さな成功体験を積み重ねることができれば、同時に定着率アップも図ることが可能です。
リスキリングを実施する手順

リスキリングの推進手順は、一般的に以下の流れで実施します。
- 従業員のスキルを可視化する
- 習得スキルとリスキリング対象従業員を決める
- 学習計画の策定・実行
- フィードバックとリスキリングの継続
従業員のスキルを可視化する
まずは各部門・部署の従業員スキルを可視化する取り組みが必要です。「現在の仕事に対してどのようなスキルセットが必要で、かつどのくらいの作業工数が発生しているのか」を可視化することで、ポジションごとの必要スキルと、そのポジションに就くための必要なリスキリングプログラムを組むことができます。ただし、DX推進では自社に存在しない新しいポジションを創出し、そのポジションに就くための道標を作成するシーンも出てきます。そのような場合は、外部の教育プラットフォームと連携するなど、スキルの可視化を手伝ってもらう方法もあります。
習得スキルとリスキリング対象従業員を決める
従業員のスキルを可視化し、ポジションに必要なスキルセットを把握した後は、リスキリング対象社員を決めていきます。大企業の場合は全社的にリスキリング計画を立てることもありますが、中小企業ではリスキリングプログラムに参加する中心メンバーを選出します。この時、リスキリングプログラムに参加しない従業員を放置するのではなく、全社的な勉強会を開くなどして情報共有に努めることが重要です。
学習計画の策定・実行
リスキリング対象社員の選出と並行して、リスキリングプログラムの策定を進めていきます。従業員のスキル可視化の精度が高ければ高いほど、特定のポジションに就くために必要なスキルセットが特定しやすくなり、習得にかかる目安時間が判断しやすくなります。また、実際にリスキリングプログラムを実行する際は、外部パートナーと協力して進捗管理を依頼することも重要です。全て自社で管理しようとすると、現場社員への負担が増加するため、外部のプロの力をかりて推進することを検討しましょう。
フィードバックとリスキリングの継続
リスキリングプログラムの実行後は、リスキリング対象社員の成果を評価し、継続的な学びを続けるための仕組みを構築しましょう。例えば「新しいスキルを習得した社員を別部門にインターンとして配属させ、数ヶ月の実務経験の後にリスキリングの成果を判断する」といった工夫が必要になります。
リスキリングを実施する際のポイント

ここまで、リスキリングの手順について説明してきましたが、うまく実施するためには押さえておきたいポイントもあります。次の5つのポイントについて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
- モチベーションに配慮する
- 従来のOJTとの混同を避ける
- 外部の研修コンテンツも活用する
- 学習を継続しやすい環境をつくる
- 学習の成果をトラッキングする
モチベーションに配慮する
リスキリングにおいて、従業員のモチベーションはぜひ配慮したいポイントのひとつです。
実際に学習することを求められる従業員は、すでに業務を抱えている状態でしょう。そのうえで新しい知識やスキルについて学ぶのは、一定のストレスを伴うことだと考えられます。まずはリスキリングを実施する意図やメリットについて、しっかりと説明しておくことが大切です。
リスキリングによって新たに得た知識やスキルが、業務のみならず、各人のキャリアにも役立つことを示せればモチベーションのアップにつながるでしょう。たとえば、資格取得を促して学習の成果をキャリアプランに取り込めるようにするなどの工夫も効果的です。
従来のOJTとの混同を避ける
学んだことを業務に活かすために、現場での実践を通したスキル向上が重要となるケースは少なくありません。OJTは、そのために有効な手段のひとつです。日本企業の強みはOJTにあるともいわれており、実際に多くの企業がOJTを実施しています。
ただし、従来のOJTは、既存業務の延長線上にあるスキルの獲得に効果を発揮するものです。これに対してリスキリングで求められるのは、これまでとは別の「新しいスキル」の獲得だという点に留意しましょう。とくにDXにおいては、業務内容の大幅な変化に適応できるスキルを身につけていく必要があります。これを機に、OJTのあり方についても再考してみるとよいかもしれません。
外部の研修コンテンツも活用する
リスキリングにおいては、外部から取り入れた研修コンテンツの活用もポイントとなります。
リスキリングを通して新たに獲得しようとしている知識やスキルは、現時点では社内に不足していると考えられます。そのための学習コンテンツを自社のみの力で制作するのは、簡単なことではないでしょう。デジタル技術にとくに強い企業でないならば、内製にこだわらず、外部で制作されたコンテンツの活用についても検討する価値があります。
デジタル技術に強みがあり、システムの内製化を得意とするような企業だとしても、外部コンテンツの活用にはコストを抑えられるなどのメリットがあります。
学習を継続しやすい環境をつくる
リスキリングの効果を高めるには、継続的に学びやすい環境を整えることもポイントです。
それぞれの従業員が、個別のタイミングで学習できるような環境があるとよいでしょう。それには、集合研修よりも時間と場所の制約を受けにくい「オンライン講座」にするのがおすすめです。既存業務があるなかでも、限られた時間を有効活用できるようになります。
また、各自の学習をサポートできる仕組みがあると理想的です。たとえば、すでにスキルを身につけた人が学習者の進捗を確認したり、必要に応じてアドバイスをしたりできる体制を整えれば、着実なスキル習得を後押しできるでしょう。
学習の成果をトラッキングする
リスキリングの効果をどのように測定するかについては、事前に検討しておきましょう。従業員各自の学習の成果を、どのようにトラッキング(追跡)するかということです。
オンライン講座であれば、受講状況を把握できるシステムを用意するのはそれほど難しいことではないでしょう。ところが、OJTに移行したとたんに、学習が進んでいるのかどうかが見えなくなってしまうというのはよく聞かれる話です。
こうした事態を防ぐには、配属先などにかかわらず学習の進捗データを収集・可視化し、成果を把握するための共通の仕組みを構築しておくことが大切です。データが集まれば、学習コンテンツの改善などに役立てることも可能でしょう。
リスキリングの実施で活用できる助成金

リスキリングをするとなると、研修費などの費用がかかってなかなか実施に踏み込めないという企業も少なからずあるでしょう。そこで、ここではリスキリングの実施で活用できる助成金をご紹介します。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金とは、従業員に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中 の賃金の一部を助成する制度です。厚生労働省が管轄していて、法人企業が助成対象となります。人材開発支援助成金は以下の7つのコースがあります。
詳しい申請の方法や受給要件などは、厚生労働省のウェブサイトなどをご確認ください。
- 人材育成支援コース
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するコース。
- 教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練等制度を導入し、労働者が有給休暇を取得して訓練を受けた場合に助成するコース。
- 人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するコース。
- 事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するコース。
- 建設労働者認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成するコース。
- 建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するコース。
- 障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成するコース。
教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、厚生労働大臣が指定する約15,000講座の中から任意の講座を受講し、教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される制度です。働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的としています。
厚生労働省が管轄していて、個人が助成対象となります。ただし、「現在雇用保険に3年以上加入している人」もしくは「離職後1年以内で、雇用保険に3年以上加入していた人」などの受給要件があるので注意しましょう。
給付金の対象となる教育訓練は、以下の3種類があります。詳しい内容については厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
- 専門実践教育訓練
対象の講座には、介護福祉士や看護師など業務独占資格などの取得を目標とする講座、ITSSレベル2相当以上の情報通信資格の取得を目標とする講座などデジタル関係の講座、大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程、専門学校の過程が含まれます。
- 特定一般教育訓練
対象の講座には、介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種・第二種免許などの業務独占資格などの取得を目標とする講座やITSSレベル3相当以上の情報通信資格の取得を目標とする講座などデジタル関係の講座が含まれます。
- 一般教育訓練
対象の講座には輸送・機械運転関係、税理士、 社会保険労務士、TOEIC、簿記検定など資格の取得を目指す講座や、修士・博士の学位などの取得を目標とする課程が含まれます。
DXリスキリング助成金
DXリスキリング助成金は、従業員に対して、民間の教育機関等が提供するDXに関する職業訓練を実施する際に、関わる経費を助成する制度です。公益財団法人 東京しごと財団が管轄していて、東京都内の中小企業等を対象にしています。
対象の訓練内容の例としては、DX推進のためのマネジメント講座やリモートワークやクラウド整備に伴う情報セキュリティ対策講座、業務効率化のために実施するExcelマクロVBA入門講座などがあります。
詳しい申請の方法や受給要件などは、東京しごと財団のウェブサイトなどをご確認ください。
国内外のリスキリング推進事例

アメリカでリスキリングの先駆的な存在として知られるAT&Tは、2008年に行った社内調査で、「従業員25万人のうち、事業に必要なサイエンスやエンジニアリングのスキルを持つ人は約半分に過ぎず、約10万人は10年後には存在しないであろうハードウェア関連の仕事に従事している」と分析しました。そこで2020年までに必要なスキルセットを特定し、現状のスキルセットから移行するための道標「ワークフォース2020」を作成しています。
ワークフォース2020では、①必要なスキルセットを習得する人材に報酬が支払われ、さらに②従業員が社内の就業機会を検索し、該当部門の今後の展開や賃金範囲を入手できる透明性の高い「キャリアインテリジェンス」を導入しました。そして、③外部の教育プラットフォームと連携して実務スキルを習得し、リスキリングを実施した従業員が一定期間新しいポジションを試せる社内インターンを実施しています。
こうしたAT&Tのリスキリングのキーワードは「透明性」と「自律性」です。企業がリスキリングを強制するのではなく、「社内の人材リソースを可視化し、既存/新規ポジションに就くために必要なスキルセットを公開すること」が成果へと繋がるとしています。AT&Tはワークフォース2020によって、社内の技術職の81%が社内異動によって充足し、リスキリングプログラムに参加した従業員の離職率は、未参加の従業員に比べて1.6倍低い結果となったと報告しています。
参考:リクルートワークス研究所「第4回 リスキリングの先駆者は何に取り組んだのか」
日本国内では未だAT&Tのように成果を挙げている企業はありませんが、大企業を中心に「DX文脈におけるリスキリング」が実施されています。弊社でもDX支援のサービスをいくつか提供しており、今回はDX推進初期に全社的な目線合わせを目的とした「DXリテラシー講座」と、3ヶ月で即戦力人材を育成する「AIエンジニアリング講座」を受講した株式会社ランドコンピュータ様の推進事例を紹介します。
株式会社ランドコンピュータ様は、長きにわたりシステムインテグレータとして顧客に価値を提供してきた企業様です。その豊富な知見と経験に加え、この度問い合わせが増加している「クラウド・IoT・AIに関する技術実装・システム開発」に対して対応するため、弊社の「DXリテラシー講座」と「AIエンジニアリング講座」をご受講いただきました。
株式会社ランドコンピュータ様は、弊社のサービスをご活用いただいたことで、「そもそもお客様の要望が実現できるのか、どのくらいの期間が必要になるのか、ということが正しく伝えられるようになった」と成果を感じておられます。
また、「AIエンジニアリング講座を通して根幹技術への理解が深まったため、内容の具体的なイメージが湧くようになり、例えば各種モデルで必要となるデータの種類やデータの処理、モデルの長所・短所等を具体的にイメージできるようになり、なぜそのモデルを活用したのかという背景や目的が理解できるようになった」と振り返っておられます。
株式会社ランドコンピュータ様のリスキリング推進事例のように、従来の業務では対応出来なかったケースにも、リスキリングプログラムの実施によって対応できる可能性があります。DXの本質は顧客起点の価値創出にありますので、こうした顧客の問い合わせから実際のサービスへと繋げていく姿勢が重要になるでしょう。
リスキリングで活用できる「デジタルスキル標準(DSS)」
 経済産業省とIPAが公開している「デジタルスキル標準(DSS)」は、DXの人材育成ための公的な指針です。以下では、デジタルスキル標準とは何なのかを説明し、自社での人材育成に活用していくポイントを解説します。
経済産業省とIPAが公開している「デジタルスキル標準(DSS)」は、DXの人材育成ための公的な指針です。以下では、デジタルスキル標準とは何なのかを説明し、自社での人材育成に活用していくポイントを解説します。
デジタルスキル標準(DSS)とは
「デジタルスキル標準(DSS)」とは、DX推進においてどのような人材を育成・採用していくべきかをわかりやすく示した指針です。
DXを実現するには、経営者はもちろん従業員一人一人もDXを自分事として関心を持ち理解した上で進めていかないといけません。そのためには、全てのビジネスパーソンがDXに関するリテラシーを身につけ、企業は専門性を持った人材を確保・育成することが必要となります。そこで、DX推進で必要となる人材育成の指針を示すデジタルスキル標準(DSS)が策定されました。
デジタルスキル標準は以下の2つで構成されています。
- 「DXリテラシー標準(DSS-L)」
- 「DX推進スキル標準(DSS-P)」
「DXリテラシー標準(DSS-L)」とは、DXに関する基礎的な知識やスキル・マインドを身につけるための全てのビジネスパーソンに向けた指針です。DXは、全社一丸となって取り組んでいく必要があります。そのため、「DXリテラシー標準」では、働く人がDXに参画できるように、DXを進める上で必要となるマインド・スタンスや知識・スキルを示す、学びの指針として策定されました。
「DX推進スキル標準(DSS-P)」とは、DXを推進する専門性を持った人材を育成・採用するための企業に向けた指針です。ここでは、DX推進に必要な人材類型として、ビジネスアーキテクト、デザイナー、データサイエンティスト、ソフトウェアエンジニア、サイバーセキュリティの5つの人材類型を示し、それぞれのロールと必要なスキルを定義しています。
デジタルスキル標準(DSS)の活用ポイント
デジタルスキル標準(DSS)を、自社で活用していくためには以下のポイントが大切となります。
- 自社のDX実現のために必要となるスキル・人材を定義する。
- 自社に必要なDX人材を育成するための教育を行う。
- 従業員が学んだことを実践できるよう実務で実践の機会を作る。
まず、「DX推進スキル標準(DSS-P)」を参考にして、自社のDXではどのようなスキルや人材が足りていないのかを考え、必要となるスキルや人材を定義しましょう。
自社に必要なDX人材を育成するために、従業員にリスキリングを行います。教育には、場所や時間に捕らわれずに従業員のペースで学習を進められ、進捗も把握しやすいオンライン学習がおすすめです。
従業員の学習が進んだら、それを実践で生かす機会を作ることも大切です。自社や顧客の課題を洗い出し、学んだデジタル技術を使ってどう解決できるかを考えて実行できるようになるまで従業員が育てば、DXをスムーズに進めていけるでしょう。
DX推進するなら人材育成によるリスキリングは必須
リスキリングは、既存バリューチェーンの変革をともなうDXの推進において実施される「新たなスキル習得の機会」です。スムーズかつ実用的なリスキリングプログラムを実施するには、従業員スキルの可視化、既存業務のスキルセット確認が必須のため、念入りに確認・調整しましょう。
また、従業員に対していきなりDX推進とリスキリングを伝えても、その熱量や意味を正確に感じ取る従業員は少ないことが予想されます。そのためまずは、なぜDX推進やリスキリングに取り組むのかといった説明をトップダウンで行うことが重要です。
弊社では、デジタルスキル標準(DSS)に準拠して、DX人材育成をどうやって進めれば良いのかを解説したお役立ち資料をご用意しております。デジタルスキル標準を具体的にどう自社で活用すればいいのかわからない、活用方法を知りたいという方は、下記より本サービスの資料をダウンロード頂けますので、ぜひご活用ください。